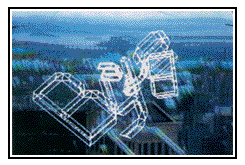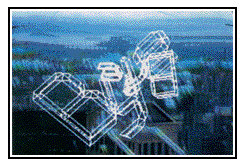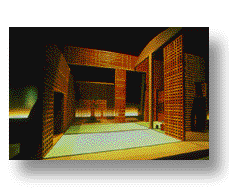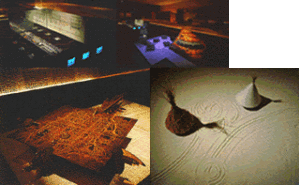半信半疑の顔をした私の前で、パイクさんは籐の籠一杯に盛られたトマトを差し出して仏陀のような顔の上に特徴のある笑みを浮かべていた。ニューヨーク中がニューウェーヴ・アートに包まれて倉庫街の非常階段までもオーヴァーヒートしそうな1983年の夏のことである。
床には破れ紙に描いたばかりの大西洋岸の地図があり、そこには主要都市を結ぶぶっきらぼうな線が伸びていた。サテライト・アート、この聞き慣れない言葉とプロジェクトのスケールの大きさは、60年代のフルクサス運動についてのインタヴューを試みようとソーホーのロフトに意気込んでやってきた私を当惑させるに充分なものだった。しかし、目の前に展開しているサテライト・プロジェクト「グッド・モーニング・ミスター・オーウェル」の真価を、その時はまだ理解していなかったのは言うまでもない。
今振り返ってみれば、ナム・ジュン・パイクのサテライト・アートの原点となったのは81年にパリのポンピドー・センターで発表された「トリコロ一ル・ヴィデオ」ではないかと思う。当時、パリの同じアパートに住むという幸運に恵まれた私は制作過程までも目のあたりにすることができたのだが、非常に工学的なプロセスとエステティックな結果の対比に息を呑んだものだった。規則正しく並べられた400台のモニターテレヴィジョンは4台ごとのユニットに分割され4種類のヴィデオ・ソフトが映し出されていた。そしてその全体を赤、白、青のトリコロールが波状に流れていく。「トリコロール・ヴィデオ」の注目すべき点は正にこのエレメントの相乗性と、イメージを端末と限定し、その増殖をネットワーキングすることで想像力の中枢、つまり、コンセプトの重要性を認知させたことにある。そして、もう一つ忘れてならないのはトリコロールの波に込められた時間軸の主張である。ヴィデオ・アートが生まれるまで美術のなかでどうしても処理できなかった問題が時間である。時は常に作品の外にあり、社会との決定的な差異は時を共有できないところにあった。近代以降のリアリズム潮流においてこの差異は実に大きな欠落だったと言わざるをえない。
20世紀に入って、ダダのソワレを発端とするパフォーマンスという形式が登場したことは、その事実を顧みれば革命的な現象である、と言っていいだろう。マルセル・デュシャンのオブジェも同様だ。前者は作品を廃棄することで、また後者は作品概念を転換することで動的なもの、すなわち、時間のダイナミズムを獲得しようとしたのだ。
だから、この作品の最終的なサーフェイスにおいてトリコロールが波状に繰り返されていたことはヴィデオ・アートの存在理由を誇示していると受け取っても差し支えなかっただろう。
これらの背景から「トリコロール・ヴィデオ」を分析すれば、この映像モニュメントがサテライト・ア-トの重要な里程標になったことを指摘することは困難なことではないだろう。例えば、これは映像作品でありながら従来の平面という認識にはあてはまらない。キャンバスに代わって表面を支持するのはブラウン管である。しかも、それは恒常性を意味しないし、厳格に物自体の自立性を維持しながら可変的な映像を時間的に処理していく。言い換えれば、モニターは作品と物の間を絶えず往来しているのであって、それは時間的に区切られたレディ・メイドとさえ呼べるものである。この作品においてはアートは信号なのだ、と理解するしかない。なぜなら、電気を通じて送り込まれる信号によってサーフェイスがその価値を変化させる以上、アートの原因はその信号自体にあると考えるべきである。しかも、それは目に見えないものなのだ。
「トリコロール・ヴィデオ」はパイクのヴィデオ・アートの集大成だったに違いない。そして、彼のデュシャン的コンセプトと、信号が届くかぎりマルチプル化を可能にさせる現代テクノロジーの出会いは必然的に極限的な自己拡大を目指すようになる。「グッド・モーニング・ミスター・オーウェル」は無限の端末と拡散された空間、そして、複合化された時間をもつヴィデオ・アートであると同時に、ヴィデオ・アート自体の限定を打破するためのデジタル・アートなのだ。この次元において目的とされるのは、モニターに映る画像以上に重要なのは、モニターさえあればアート・シグナルを受信できるという可能性である、という意識の確立である。
シグナルに還元されたアートを社会現象に照らしあわせながら考察してみると、そこにパイクがアートに果たそうとしている明らかな功績を見ることができる。その為には、アートは元来、作品ではなく宇宙観であったことを思いださなければならない。
厳密に言うならば人間の知性を基準とした哲学を初めて示したソクラテス以前、また、キリスト教がヨーロッパに到達した以降の社会に限定しても、ルネッサンスさえも超えて、おそらくデカルトまで、アートが提出し続けてきた映像は個人の認識を超えたところにある宇宙像の提出をその目的としてきた。これは一種の情報システムであり、作品はアーチストから発信されたメッセージであり、宗教が発信者と受信者を結ぶ共通コードだった。この場合、アーチストは神の代弁者とみなされ、受信者即ち大衆は自らの合目的的活動の達成のために彼らのメッセージを受容する。その目的が彼らの日常と重なることは言うまでもない。神の世界に昇華するという目的は確率的には非常に低いことであるから、情報理論的な視点から見れば情報そのものの価値は反比例的に大きくなる。近代以降のアートの歴史は神に代わる人間の自我、つまり発信者の多元化とそれにともなうコード(言語体系)の転換による確率の増大と情報性の低下のそれだと見ることもできるだろう。近代において、アートが作品至上主義に転化したことの原因のひとつにはこの情報性の低下が挙げられると思う。この現象は産業革命以後、急速に発達する流通経済社会においても好都合なことだったに違いない。
このような経緯を踏まえて考えると、今世紀初頭、レディ・メイドで作品概念を廃棄しようとしたマルセル・デュシャンが訴えようとしていた意味の根本的な部分に、アートにおける情報性の回復と、多元論のマキシマムな一般化による一元論化を基にするコミュニケーションの復活が含まれていたと考えることは容易なことではないだろうか。デュシャンがレディ・メイドの作品についてはオリジナルを残そうとしなかったことからも、彼が目的としていたことが単なるユーモアの範疇に属するものではなかったことは明らかだろう。つまり、今日的な表現をあてはめれば、作品は一種のパスワードのような役割を果たすものなのだ。
しかしながら、この試みには従来のアート概念にとっては一種の危険がともなっている。それはアートの不可欠な成立条件であり続けてきた映像とその創造までをも否定される可能性を秘めているからである。20世紀において彼の思想を最も良く理解し、また前進させた2人、ジョン・ケージとパイクがともに音楽家だったことはこの点において非常に重要である。音楽には、アートに欠けていた要素がある、時間とパフォーマンスである。音楽作品の価値は作曲家の残した楽譜にそのすべてがあるのではなく、限定された時間内に行われるその解釈と伝達によるコミュニケーションに多くのものを負っている。そして、この解釈者によるパフォーマンスは近似値の範囲内ではあるが、リプロダクションによるコミュニケーションの再現も可能である。詩の領域において、もっと音楽を、と主張したのはヴェルレーヌだったが、アートにおけるその導入はもっと本質的で現実的な部分での改革を示唆していた。
現代音楽からフルクサスのイヴェントへと進んだパイクの軌跡がヴィデオと出会うことは、この音楽性の導入という意味においてもアートにとっては奇跡的な出来事だった。私たちは初めて時間を持つ造形芸術、もしくは、純粋映像に覆われた時間を手にしたのである。ここで忘れてならないのは、時間を表現する映像と動くだけの映像は違うということだ。口にだすと単純な問題に思われるかもしれないが、これはその後現れた多くのヴィデオ・アーチストが犯した間違いである。確かに、パイクは新しいアート・ヴィジュアルを提出したかもしれない(そして、そのクオリティについては「グローバル・グルーブ」などの作品を超える作品が未だに出現しないことでも証明されるだろう)、しかし、彼が着目しつづけているのはアートにおける第三のメディアとも呼べるものの創造であり、そこではすでに従来の作品概念は通用しないことを我々はもう一度確認しなければならない。さもないと、「グッド・モーニング・ミスター・オーウェル」も「バイ・バイ・キップリング」もだだの出来の悪いヴァラエティTV番組になりさがってしまうだろう。時間と文化と空間を映像でネットワークし、クロスオーヴァーさせること、それがパイクの目的であり、テクノロジーを新しい自然とする現代文明のアートなのだ。
「1984」で機械文明の未来に警告を与えたオーウェルも、まさかその同じ年に、しかもアーチストの手でその反語が送り出されようとは思ってもいなかっただろう。しかし、1984年1月1日、機械によって電波化された文化は大気圏の至る所で交差し、人間のコミュニケーションに新たな可能性を与えたのである。
当日、ニューヨークとパリの収録現場に集まった出演者の顔ぶれは、ヨゼフ・ボイス、ローリー・アンダーソン、ジョン・ケージ、ジョン・サンボーン、マース・カニングハム、イブ・モンタン、ピーター・ガブリエル、トンプソン・ツインズ、フィリプ・グラスなどなど、彼が私に最初に話したときに使った表現「オールスター・ヴィデオ」そのものの豪華メンバーだった。パイクは企画、構成、演出をすべて一人でこなし、そのうえ、費用の捻出、各国放送局との交渉まで行ったのである。キー局となったニューヨークのWNETはボストンのWGBHを中心にネットされるノンプロフィットのPBSネットワーク局で、視聴者の寄付と各番組ごとの独立採算性をとるユニークなシステムをもつテレビ局だが、実質的にはアメリカ最大の放送網を持っている。このパイクのプロジェクトには願ってもないようなシステムをもつ国は、今のところアメリカしかない。つまり、パイクは経営形態もシステムも異なる各国の放送局を個人の力でネットワークしようとしたのである。そのことだけをとっても彼が自らのパフォーマンスで引き起こした混乱は、番組のなかだけには留まらないことが分かるだろう。
残念ながら、日本では同時放送は実現しなかったが、今は亡きボイスのパフォーマンスをはじめ数々の貴重なシーンをドキュメントした「グッド・モーニング・ミスター・オーウェル」は20世紀芸術の歴史的な事件として記憶されることは間違いないが、現象的な事実を追う者にとっては、意図的であるにしろないにしろ、引き起こされた混乱が正当な理解を妨げたこともまた事実である。例えば、フランス側の放送に顕著に現れたように、テクニカルな問題はそのままこのプロジェクトの本質にかかわるものである。特にスウィッチングに関する混乱は「電波を使用するバフォーマンス」もしくは「広域化したアート」における今後の問題を示唆している。
将来、マスコミュニケーション・テクノロジーが発達するにつれて解消される問題ではあるが、現在の時点では、このようなプロジェクトの進行にあたって多数のスタッフの動員は避けられない条件である。しかしながら、いかに自己拡大を遂げようとも、すべての芸術がそうであるように、アートの表現は個人の言語体系とインスピレーションによって成り立っている。問題はマザー・コンピューターに接続された端末機と違って、人間はその数だけ固有の言語体系と情報システムを所有していることである。それゆえ、パイク自身のインスピレーションと言語は距離と人為的な原因による二重の時差を併せ持つ結果となってしまった。人類がアートにたいして作品中心の概念を抱いている限り、絵筆やノミを使用した作品のように個人的な技術がダイレクトに見る者に伝わらないこのような作品は明らかに大きなハンディキャップを負わなければならない。それでも、あえて実行したところに彼の勇気とこれからのアートに対する確固としたヴィジョンを見ることができる。
すなわち、限定された時間内に行われる行為とコミュニケーションこそが未来に向けて私たちが到達すべきアートなのだ、という主張である。
「グッド・モーニング・ミスター・オーウェル」で示されたパイクのコンセプトは86牛に実現した次なるプロジェクト「バイ・バイ・キップリング」でより明確に表現されることとなった。アジア大会の最終日に行われるマラソン競技に時間を合わせて、ソウルからのマラソン映像とニューヨーク、東京で同時進行するカルチャー・プログラムをサテライトによる相互通信方式で交差させるという筋書きは、時間についての認識を効果的に強調するものであるし、大西洋に続き太平洋カヴァーするこのプロジユクトでもう一つの重要なファクター、宇宙空間性が現実的に把握されるようになった。

プログラム自体は、アルヴィン・エイリー、デヴィッド・ヴァン・ティーゲム、ルー・リード、キース・ヘリング、フィリップ・グラス(ニューヨーク)、三宅一生、横尾忠則、坂本龍一、磯崎新、山海塾、小錦(東京)らの出演によるオールスター・カルチャー・ヴァラエティ的な構成は変わらなかったが、ヴィデオ素材の多用など、前回の経験を生かした組み立てを用いることで番組のリズムに変化をもたらしていた。

ただ、今回はマラソンという全く構成のきかない100%ライヴのイヴェントを取り入れたために、各ステーションにおける時間合せへの努力は前回以上の細心さが必要だった。特に、日本ではNHKというノンプロフィットの放送局が放映を受諾しなかったので一層複雑なものとなった。なぜなら、コマーシャルの差し込み、アジア大会の放映権の問題などアメリカや韓国では考えられなかったファクターが入り込んできたからである。
パイクのサテライト・プロジェクトは彼のヴィデオ作品がそうであるように、一種の交響性の上に成り立っている。彼が図解する台本を見れば一目瞭然だが、まるでジョン・ケージをほうふつとさせる現代交響楽の楽譜を見るようである。この場合、指揮者は当然パイクだが、ハーモニーやシンクロ、そして現実性までをもコンダクトする現代の指揮者=作曲家と違って、地球全体をそのコンサート・ホールにしているだけに、サテライト・プロジェクトにおける彼の立場は社会的現実・時間に翻弄されなければならない。インターナショナル・ライブであるかぎりリハーサルも不可能である。
しかしながら、20世紀におけるアートと音楽の歴史に照らしあわせてみると、パイクの目指すところがその極点であることがわかるだろう。今世紀初頭、チューリッヒの場末のキャバレーでダダイストたちが、ソワレと題して口火を切ったアートと現実の再結合がその形を壊すことなく彼のプロジェクトの中に結晶しようとしている事実を私たちは見逃してはならない。
様々な問題を抱えながら「バイ・バイ・キップリング」はスタートした。結局、サテライト2WAYイヴェントの日本での同時放送は実現しなかったし、ビールの注ぎ合いを始め相互の物理的文流を演出しようとした試みの多くはスラプスティックとさえ言えるほど、見事に失敗した。しかし、それにもかかわらず多くのアーチストを引きつけ、異なる国籍の人々を感動させた事実を私たちは注視しなければならないだろう。
当日、東京会場(アークヒルズ)でディレクションを行ったパイクの方法を見ていて興味深かったのは、まさに行き当たりばったり、という表現がぴったりするほどそれは直観的で、本番中でさえインスピレーションによる対応、変更を指示していた。秒刻みのタイム・テーブルと周到な準備に基づいて進行される現在のテレビ番組ではおそらく許容されない方法を、しかもメイジャー・ネットワークで、彼が独自な方法で実行している現場を目の当たりにすると、共有する時間とメディアの中で人間の形而上的な感覚を交差させて到達する完成こそが彼が求めるものであり、パイク自身はその媒介者となることが目的ではないか、と考えてしまう。最新、最高のメディア・システムにおいて人間が所有する性質の中でおそらく最も原始的なものを自由に解き放つ、CULTから派生したCULTUREの語源にまで思いを起こさせるこの意識にそパイクの到達したアートについての最終概念ではないだろうか。
今年(88年)ソウル・オリンピックの文化行事としてパイクの最後のサテライト・プロジェクト「スポーツ・オン・ザ・ロックス」が実現する。その企画書の冒頭で彼は「スポーツとアートは異なる民族を結ぶ最も強力なコミュニケーショシ形式である」と宣言している。おそらく、今回パイクはより明確な姿勢で新しい(若しくは原初的な)アートの実行に臨むだろう。そして、当初彼が予定していたタイトル「地球大風呂敷」のごとくに電波は地球全体を包むに違いない。それは裏を返して言えば、純合理的に構築されたハイテク・メディアにまでも心象構造を注入した人間の勝利でもある。
戦後、他国に文化を求めて東へと旅立ったパイクは数十年の時を経て、自らが創造した新しい人間の文化遺産を携えて西方から帰国する。それは彼が言うように遊牧民の血がそうさせたのかもしれない。少なくとも、彼は現代のシルク・ロードの在り方を示していることは間違いない。
バイバイ・キプリング
ナム・ジュン・パイク氏のサテライト・パフォーマンス。
アメリカPBS(WENET)全米280ネットワーク(1986年10月4日午後9時~10時30分)と、日本JCTV(10月5日午前10時~11時30分)で衛生中継された。
録画編集版”Bye Bye Kipling”は、テレビ朝日系で全国にネットワーク(10月5日午後1時50分~2時45分)放送。4日後韓国でも放映。