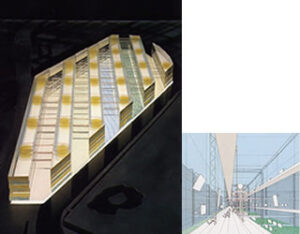チェコ語で強制労働者を意味する「ROBOTA」が、近代主義文明の象徴として、仮想の人間型機械のネーミングに使用されてから60年以上の月日が経っている。その間、多くの場合、ロボットはヒューマニズムの敵のように扱われ、行きすぎた科学文明批判の材料に使われてきた。
しかし、そのイメージを画期的に変える「ロボット」像が50年代に日本から発信されたのである。
「鉄腕アトム」と名づけられた科学の子は、時として、汎技術の危険性を見せながらも、その並外れた能力で人間を助け、また、時には、人類の欺瞞を指摘して見せた。
利益追求に偏った近代主義文明において、半ば死語となった「正義」という概念を、この金属の塊は鮮やかに表現して見せたのである。人類の批評者を持つ重要さをアトムは誰にでも理解できる言語と映像で表現してくれたのである。
アトム以後、ロボット観は大きな変貌を遂げた、というよりもむしろ、ロボットのみならず、ハイパーテクノロジーにおける「倫理」への訴求が問題にされるようになったのである。
後に、ドゥールーズ=ガタリが哲学的に語り始める未来の問題を、はるか以前に、手塚治虫は機械と人間のヒューマンな物語で私たちに伝えていたことを私たちは今、思い出さなければならない。
また、「アトム」は日本文化の輝かしい表象でもある。そこには芸術的なコンテンツを大衆的なインターフェースで表現するという、日本の町人文化の伝統が脈々と生きているからである。
19世紀末から20世紀初頭にかけて、ヨーロッパを席巻した「ジャポニズム」に見られるように、安土桃山から江戸時代にかけて、ブルジョワジーの台頭と共に培われた日本の町人文化は、その後江戸幕府が行った鎖国という閉塞的な状況の中で、独特の感性と技術を見につけながら、世界にも類を見ない固有な発達を遂げた。
特徴的なそのコンテンツの中でも、浄瑠璃や歌舞伎の時代物や世話物、浮世草子、川柳、浮世絵などに顕著な情報性や、木版、染色、からくり人形に代表される技術へのあくなき追及は、特にその性格の形成に重要な役割を果たした。
そして、何よりも重要なのはそのすべての分野において大衆を視野に入れたインターフェースが準備され展開されたことである。その背景には常に、近代哲学のように純粋概念的ではない、倫理的もしくは時代批評的なコンセプトが盛り込まれていたのである。
19世紀高踏派に代表されるように、多かれ少なかれ、「芸術のための芸術」という純粋概念の道を選択し、20世紀ヒューマニズムとテクノロジーの発達による大衆への大量伝達の可能性の前に、その限界を痛感していた西洋近代芸術が、良質のものを大量に供給する浮世絵や草子のコンセプトと技術を高く評価したのは、当然のことだったのである。
その系譜に連なる「アーツ・アンド・クラフト」や「バウハウス」がネットワーク・コミュニケーション時代に再評価されるのも当然のことである。
しかしながら、近代主義の輸入と共に、日本において発信者と受信者の一元化という図式が崩壊し、「芸能」や「文化」が芸術として隔離されると、その輝きも色うせてしまった。
「漫画」や「デザイン」が、21世紀を前に日本の芸術としてクローズアップされている理由は発信した日本よりも、むしろ世界の方が、日本文化が20世紀芸術のあり方に果たした貢献とその内容を記憶しているからであり、メディアとテクノロジーの発達、そしてネットワークの整備によってすべての情報と価値観が一元化されようとしている現在、流体的な思想である「倫理」と「時代」を切り口とし、「否定」ではなく「肯定」をその思想とする日本文化のオリジナル・モチーフがより多くの価値を持つことが認識されているからである。
「鉄腕アトム」は、その意味において、限りなく日本的なものの未来表現である。
原子力による悲劇を経験した日本人でありながら、テクノロジーをいたずらに否定するのではなく、真に批判しなければならないものを、手塚はここでやさしく、美しく説いている。
同時期に現れた「鉄人28号」、後に続く、「マジンガーZ」、「ガンダム」などと共に、人間の鏡としてロボットを捉えることで、人間とロボットの関係性は成立し、意識の中で、ロボットの必要性が生まれたのである。
そのような流れの中で「AIBO」や「WABO」が誕生した。ここで私たちは日本における「ロボットイズム」の流れを再考し、日本のオリジナルな思想の価値を検証したいと思う。